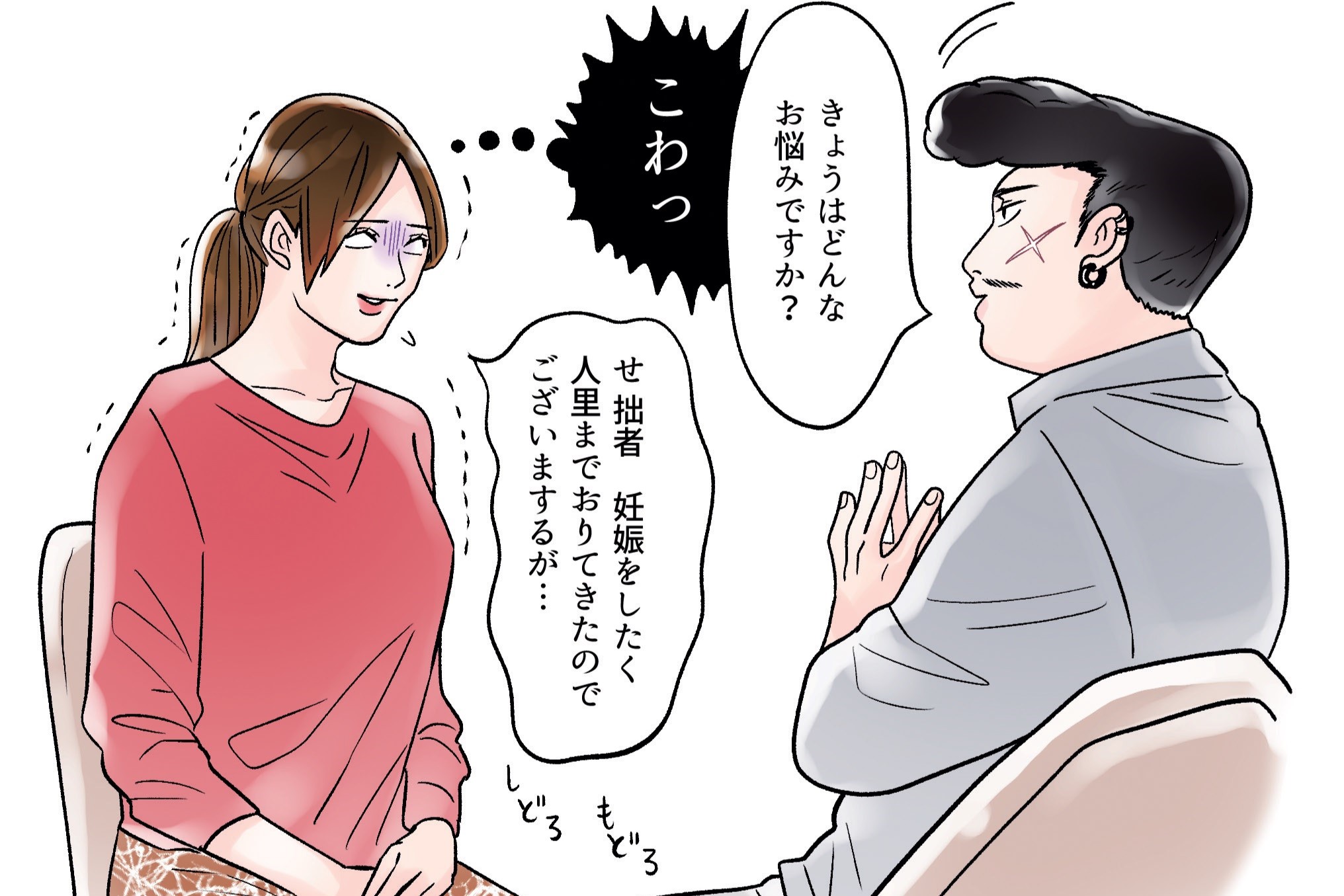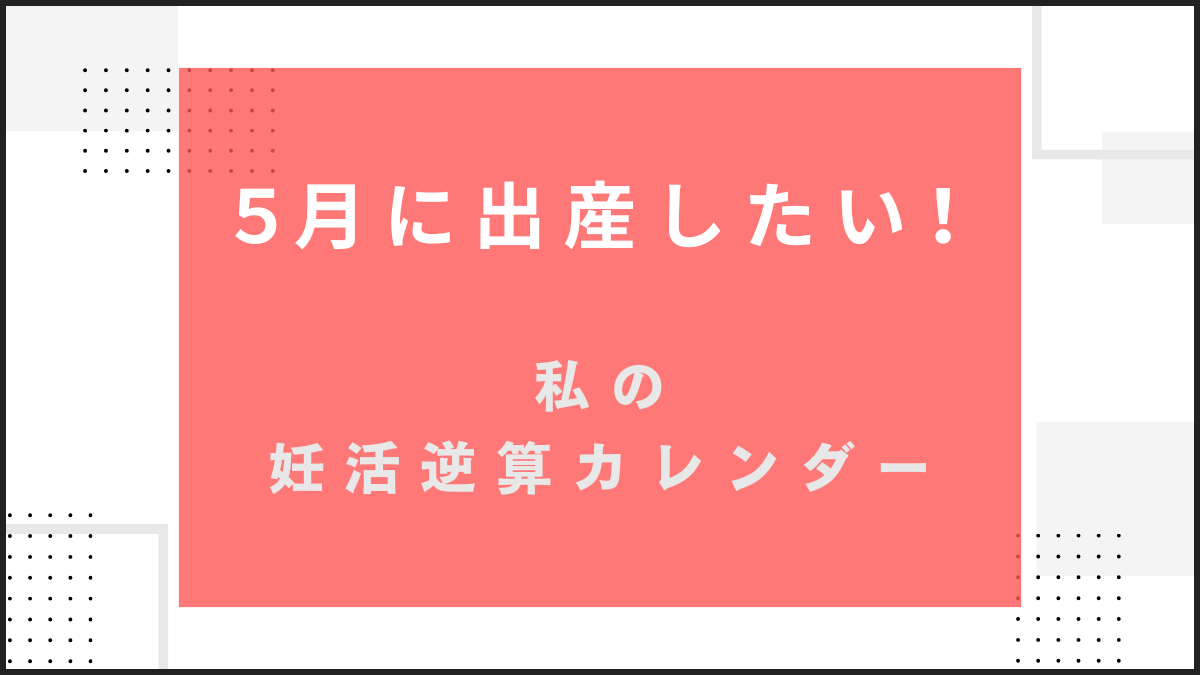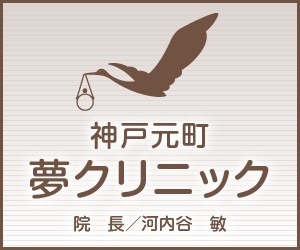不妊検査や不妊治療を受けて助成金を申請する場合、あとから「条件に合わなかった」「思っていた金額と違う」ということにならないよう、事前に助成制度について理解しておくことが大切です。
申請にあたって、申請フォームに期間や支払った額などを入力する欄があるため、クリニックや病院でもらった領収書はひとまとめにして保管しておくのがおすすめです。
また、申請には医療機関が作成する「受診等証明書」が必要ですが、それ以外の「住民票の写し」や「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」などは自分で取得する必要があります。
いかなる理由でも申請期限を過ぎたものは受け付けてもらえないので要注意!
今回は、東京都の助成事業を例として紹介しましたが、条件などが変更されることもあります。詳細や最新情報は、各自治体のウェブサイトでチェックするようにしましょう。
高額療養費制度って何?不妊治療も対象になる?
高額療養費制度とは、医療機関や薬局で1ヶ月(1日から月末まで)に支払った額が「自己負担限度額」を超えた場合に、加入している健康保険組合や国民健康保険などから、超えた分について払い戻しを受けられる制度です。
保険が適用される医療費が対象のため、先進医療など自由診療(自費)を受けた場合は対象とならないので注意が必要です。
月をまたいだ場合は月ごとに支払った金額を計算し、自己負担限度額を超えた分が払い戻しの対象となり、合算はできません。ただし、同じ世帯で同一の健康保険に加入している場合は、同じ月に支払った金額について合算することができます。
たとえば、不妊治療で3月に7万円、4月に6万円を支払った場合は、13万円として申請することはできません。一方で、夫が被保険者の健康保険で、3月に妻が不妊治療で7万円、夫が整形外科で1万円、眼科で1万円支払った場合は、合算して9万円で申請が可能です。
自己負担限度額は年齢や所得によって区分されているので、加入している健康保険組合や市区町村のウェブサイトなどで確認しましょう。
医療費控除も受けられる?
その年の1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の合計額が10万円以上(*)であれば、確定申告をすると所得税と住民税の減額が受けられます。日常生活にかかる費用など生計をともにしていれば、本人以外の配偶者や家族の医療費も合算できます。
*総所得金額「給与所得控除後の金額」が200万円未満の場合は総所得の5%
医療費控除は、実際に支払った医療費の合計額から、保険金などで補てんされる金額(健康保険の高額療養費など)を差し引いて計算します。
不妊治療でも、人工授精や体外受精・顕微授精などの費用、通院のための交通費など、“治療を目的とするもの”は控除の対象となります。くわしくは所管の税務署にお問い合わせください。
確定申告には、「確定申告書」以外に、「医療費控除の明細書(内訳書)」に医療を受けた人ごと、医療費を支払った病院ごとに記入する必要があるので、医療機関を受診した際の領収書はひとまとめにして保管しておきましょう。
取材・文/荒木晶子
〈あわせて読みたい記事〉
●【不妊治療にかかるお金】人工授精や体外受精は保険診療?どんなときに自費になる?
●先進医療って、どこで受けられる?混合診療はNGってホント?【不妊治療にかかるお金】
●妊活中の貯金額や共働き事情、夫婦喧嘩の頻度まで…赤裸々データ大公開!【妊活卒業生100人アンケート】
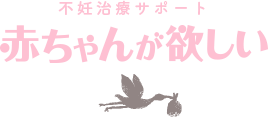

 会員限定
会員限定