【不妊治療にかかるお金】人工授精や体外受精は保険診療?どんなときに自費になる?

妊活で気になる、お金のこと。不妊治療の人工授精や体外受精が保険診療となり、窓口で支払う医療費が原則3割負担となりました。なお、受けるにあたっての条件や年齢による回数の制限などもあります。不妊治療と保険診療について、峯レディースクリニック院長の峯克也先生に聞きました。
関連記事→先進医療って、どこで受けられる?混合診療はNGってホント?【不妊治療とお金2025】
ここがポイント!
1.タイミング法から体外受精まで、基本的な治療に保険が適用される
2.保険診療を受けるためには条件がある
3.体外受精には、年齢制限と年齢による回数制限がある
4.混合診療(保険診療と自由診療を同時に行う)はルール違反!
1.タイミング法から体外受精まで、基本的な治療に保険が適用される
不妊治療にはタイミング法、人工授精という一般不妊治療と、生殖補助医療(ART)と呼ばれる体外受精・顕微授精があります。タイミング法から始めて人工授精、体外受精にステップアップしていくほか、不妊原因や年齢によっては体外受精から始める場合もあります。
不妊治療に保険が適用される前は、人工授精や体外受精・顕微授精はすべて自由診療でした。2022年(令和4年)4月からの保険適用により、タイミング法から体外受精・顕微授精まで保険で診療を受けられるようになりました。
【保険診療の代表的な項目】
<一般不妊治療>
タイミング法と人工授精(AIH)が一般不妊治療にあたります。排卵誘発剤や黄体ホルモン製剤、超音波検査、ホルモンの値を調べるための血液検査、精液検査などに保険が適用されます。
このほか、「一般不妊治療管理料」が3ヶ月に1回かかります。
<生殖補助医療>
体外受精(IVF)・顕微授精(ICSI)、男性不妊の手術(精巣内精子採取術・TESE)があてはまります。
・生殖補助医療管理料
生殖補助医療を行っている患者さんに対して、その同意を得て計画的な医学管理を継続して行い、療養上必要な指導を行ったことに対する料金。月1回算定されます。
・排卵誘発剤
・超音波検査、採血によるホルモン検査
地域によっても異なりますが、1周期におおよそ2~3回です。
・採卵
採卵個数によって料金は異なります。
・採精
・体外受精・顕微授精
顕微授精は行う個数によって料金は異なります。
・受精卵の培養、胚盤胞の培養
培養する個数によって料金は異なります。
・胚移植
・胚の凍結保存
凍結する個数によって料金は異なります。
・凍結胚の更新料
不妊治療を行っていない期間は自費となります。
・精子の凍結保存
乏精子症など、医療上必要と認められた場合のみ。
次のページ>>保険診療を受けるためには条件がある
関連タグ
- 24時間
- 月間
-
1【2025年】女の子の珍しい名前740選!キラキラネームじゃない、かわいい&おしゃれな名付けアイデア2【2025年】男の子の珍しい&かぶらない名前!古風・かっこいい名付けアイデア3妊活情報誌もらえる!あかほし会員登録(無料)しませんか?うれしい特典がいっぱい【赤ちゃんが欲しい】4【菊地亜美さん】流産、体質改善、人工授精。妊活を通して痛感した「柔軟であること」の大切さ【後編】5古風・和風な男の子の名前を厳選!かっこいい・おしゃれな名付け例35264月生まれなら、いつ妊娠?私の妊活逆算カレンダー【4月出産ママになる】7【排卵日検査薬】写真つきリアル体験談!実際に使ってみてどうだった?妊娠しましたレポートも8対象が拡大されたPGT-Aって?妊娠率は高くなるの?費用はどのくらい?加藤レディスクリニック院長に聞く9男女どちらにも使える「中性的な名前」253選!おしゃれな名付け例を紹介10【全国おすすめ子宝祈願】2026年絶対行くべき最強子宝スポット20選〜妊娠しましたレポ続々!
-
1【2025年】女の子の珍しい名前740選!キラキラネームじゃない、かわいい&おしゃれな名付けアイデア2【2025年】男の子の珍しい&かぶらない名前!古風・かっこいい名付けアイデア3〈川崎希さんの10年妊活〉不妊治療はいつもの“日常”。決して特別なものではない【前編】4【全国おすすめ子宝祈願】2026年絶対行くべき最強子宝スポット20選〜妊娠しましたレポ続々!5妊活情報誌もらえる!あかほし会員登録(無料)しませんか?うれしい特典がいっぱい【赤ちゃんが欲しい】6【杉山愛さん】40代での高齢妊娠・出産にはリスクも。夫婦で全部話し合いました!独占インタビュー②74月生まれなら、いつ妊娠?私の妊活逆算カレンダー【4月出産ママになる】8〈CYBERJAPAN DANCERS・渡辺加和さんの妊活〉卵巣も卵管も切除した私は、将来妊娠できるの?【前編】9【東京おすすめ子宝祈願2026】絶対に行きたい!最強の「子宝神社と子授け寺」10選10医学的根拠に基づいた「男の子」産み分け成功ポイントを解説!【産婦人科医監修】
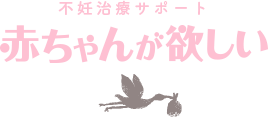









 会員限定
会員限定

